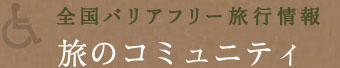![]()
住んでいる場所: 島根県松江市
一言コメント:
プロジェクトゆうあいは、人にやさしいまちづくり、情報化の推進、障がい者の社会参画支援を事業の柱とし、平成16年に設立され、平成19年より高齢、障がい者の旅を支援する事業に取り組んでいます。
松江市内、島根県内、そして山陰地方における、まちのバリアフリー情報、交通機関のバリアフリー情報を、障がい者とともに現地調査のもと整理し、マップや情報誌、ホームページを通じて情報発信しています。また、観光関連団体へのバリアフリー研修の実施、旅行者に対してはバリアフリーの旅行相談を行っています。これらの業務は松江/山陰バリアフリーツアーセンターの運営を通じて取り行っています。また、視覚障がい者外出支援連絡会JBOSの島根県の事務局も担っています。
理事長が全盲の視覚障がい者であり、職員にも視覚障がい者、聴覚障がい者が在籍していることから、視聴覚が不自由な方々への様々な情報支援の取り組みも行っています。
▼松江/山陰バリアフリーツアーセンター
(NPO法人プロジェクトゆうあい内)
営業時間:平日・土日祝/10:00~18:00
平日TEL:0852-27-0915
休日TEL:080-3873-4220
FAX:0852-27-0915
住所:〒690-0888 島根県松江市北堀町35-14
(※平成23年11月17日より新住所)
WEBサイト:http://tekuteku-sanin.com/
E-mail info@tekuteku-sanin.com